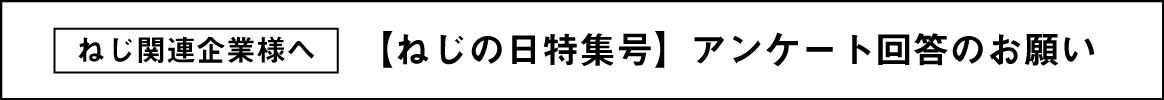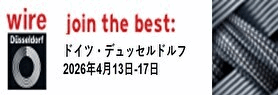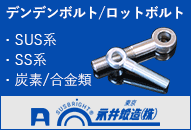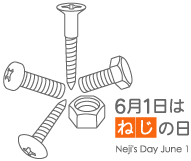昨年来の課題である物流の「2024年問題」は、低運賃や流通慣行に加え、「日本社会における物流軽視」の思想も少なからず影響していると考えられる。製造業では、物流が「無料で享受できるサービス」と見なされることが多く、企業は物流を「コスト削減の手段」としてしか捉えない傾向がある。このような考え方では、物流の改善を促進する動機が生まれず、行き詰まりを避けることが難しくなる。
物流の重要性を認識するためには、まず社会全体の思想を根本的に転換する必要がある。現代社会は物流に支えられており、物流が途絶えることは社会全体の機能停止を意味する。特に、災害時や緊急事態における物流の重要な役割は、日本ではしばしば軽視されてきた。コロナ禍では、欧米がトラックドライバーへの支援を行ったのに対し、日本ではほとんど支援がなかった。
物流業界に精通した識者によると、日本企業における物流軽視の背景には「兵站軽視」の思想があるという。兵站は軍隊の補給・輸送・後方支援を指し、物資や人員の移動を確保する基本的な仕組みだ。旧日本軍の敗北は、この軽視が原因の一つとされ、物流の重要性を軽視すると組織の機能不全を招くという見方がある。製造業では、物流が「コア業務ではない」と見なされるなど、企業内での物流軽視が続いている。
製造業で物流部門が軽視されている証として、物流担当役員がほとんどいないことが挙げられる。物流部門はコストセンターとして扱われ、企業内での優先順位が低くなりがちだ。こうした状況では、物流の効率化や高度化が企業全体の競争力向上に繋がるという認識が欠け、物流問題が放置されていることが多い。
欧米企業では物流が戦略的役割を担い、サプライチェーンの最適化を目的に責任者を配置する企業が多い。物流は企業価値向上に貢献する要素として認識され、適切に評価される。その結果、物流部門には優秀な人材が集まる。日本企業は前述の通り、物流を「コストカットの対象」と見なし、物流部門の切り捨てを進めている。特に製造業では、物流子会社の売却が頻繁に話題に上る。物流担当役員が少ない現実は、企業が物流の重要性を十分に理解していないことを示している。
2025年も早くも3カ月が過ぎ、物流業界は急速に進化している。AIやIoT技術を活用した効率化が進む中、物流の重要性は一層高まっている。物流を単なるコストセンターとして捉えるのではなく、変革に対し前向きな姿勢に切り替えねばならない。物流のデジタル化や自動化は着々と進んでおり、対応が遅れれば、企業の競争力に大きな影響を与える可能性も否定できない。