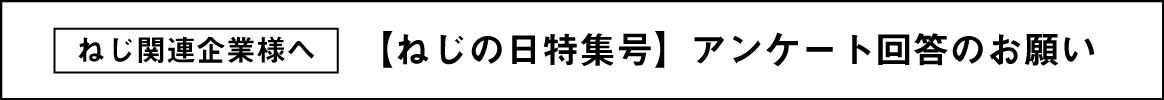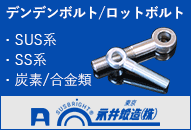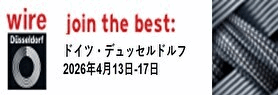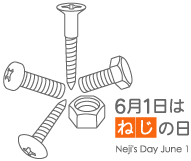1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故―。明確な原因は未だ分かっていないが、元々地盤の弱い土地だったと云われ、今のところ下水道管の破損が有力な候補に挙がっている。そのため、国土交通省は同様の事故を防ぐため、下水道を管理する全国の自治体に緊急点検を要請した。
今回の事故は大規模で行方不明者が出ているが、道路陥没や水道管破裂自体は全国でかなりの頻度で発生している。日本のインフラの多くは、戦後の1950年代前半~70年代前半の高度経済成長期、特に東京オリンピック開催前後となる60年代に整備され、設計寿命を50年~60年と考えれば、現在まさに耐用年数を迎えているのも多数あるだろう。
インフラは適切な維持管理が求められるものの、その予算確保や実行には多くの課題がある。老朽化の点検、補修、そして必要に応じた更新は、今後ますます重要なテーマとなっていく。
私たちの日常生活を支える基盤となるインフラは、経済の発展にも不可欠な役割を果たす。しかし現状では予算不足だけでなく、予算があったとしても少子化による人手不足、さらに物価高騰を含め資材不足といった複合的な課題があり、整備が進みにくい。これらの問題にどう対応するかが、今後の維持管理の大きなポイントとなる。
維持管理においては単なる補修にとどまらず、景気回復や需要・雇用創出といった側面を期待できる面もある。ニューディール政策のように、インフラ投資を通じて経済を活性化させることができれば、経済全体の成長にも寄与するだろう。特にデジタル化や環境対策を含んだ現代的なインフラ更新が進めば、新たな産業や雇用創出にもつながり、費用対効果は大きい。
ただし高度経済成長期当時の急いでの整備ではなく、現代社会のニーズに合った長期的視点での計画的な更新が求められる。地震や風水害に対しての防災性を強化する技術、環境に配慮した設備、さらにはデジタルインフラの整備が必要だ。
その中でねじ・ばねをはじめ金属加工業が果たせる役割はあるはずだ。高度経済成長期の当時よりも高品質な鋼材を使用して精密に加工され、かつ高効率でコスト面にも優れた金属部品、これらでインフラ全体の耐久性を高め、長期間にわたって信頼性を保てればなおのこといい。
道路陥没事故はインフラ老朽化の深刻さを改めて認識させると同時に、適切な維持管理と更新が急務であることを強調している。
これを契機に関心が高まり「怠ると後でそれ以上に高くつくこともある」と認識して注力できれば、次世代に向けた持続可能な社会の基盤を築くのが期待できる。