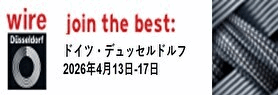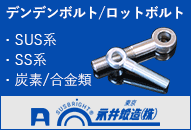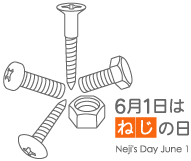2022年に事業を開始した(一社)日本ねじ研究協会(ねじ研)の「ねじ大学校」は、昨年9月に初めての卒業生を輩出した。ねじ業界の将来を担う技術者の育成を目的として設立された本事業は、業界の発展に貢献する専門家を養成することを目指しており、同事業の発展を期待したい。
初の卒業を機に、「ねじ大学校」の設立経緯やこれまでの取組みを記した、ねじ研の人材育成委員会委員長の北井敬人氏(ケーエム精工㈱)が『日本ねじ研究協会誌 第55巻 第10号(2024)』に寄稿したが、本号ではこれをまとめて掲載している。
これによると、「ねじ大学校」の設立は、ねじ研の会員減少を食い止めるための取り組みの一環として、2020年の一般社団法人化移行に伴う組織改正を機に構想された。当初の目的は、ねじ研を担う技術者の育成だったが、ねじ業界全体の発展に貢献できる技術者を養成する方向へと目標が拡張され、「ねじ大学校」の構想が具体化した。
教育プログラムは、海外のねじ技術者教育プログラムを参考にしながら、ねじの基礎から設計・製造、締結技術、信頼性向上までの13分野にわたり、58の学習項目を設定した。さらに、既存の講習会の活用とともに、新たな講座の開設やOJTの導入を図り、単なる知識習得に留まらず、実践的な問題解決能力の向上を重視した。また、講習受講後のレポート提出や理解度確認試験を必須とし、所定の単位取得と卒業試験の合格をもって卒業認定が行われる制度を整えた。
2022年7月には、ねじメーカーやユーザー企業の社員を含む6名の1期生が入学し、2年間のプログラムに取り組んだ。その後、受講者の要望を反映し、講座の追加や制度改善が進められた結果、2024年9月時点で38講座(242単位)にまで拡充された。これに加えて、学生間や講師との交流不足を解消するため、対面学習報告会の義務化やチューター制度の導入が図られ、学習の継続と競争意識の醸成に寄与している。
同事業の成果として、2023年9月には2期生として8名が入学し、初の女子学生も受け入れられた。さらに2024年には3期生3名が新たに加わり、徐々に規模を拡大している。今後は、標準化委員会や国際会議へ貢献できる人材の育成が求められ、標準化コースを設置し、国際標準化の意義を理解し提案を理論的に説得できる人材の育成を目指す。
「ねじ大学校」が継続的に発展し、より多くの企業から学生が集い、卒業生がねじ業界の未来を牽引する存在となることが期待される。業界全体でこの取り組みを支え、教育の充実を図ることが求められる。