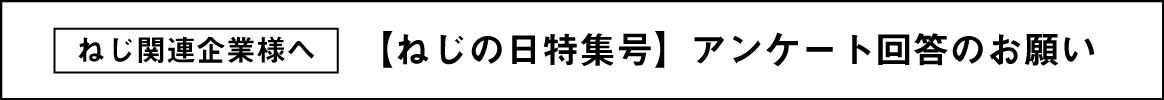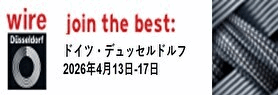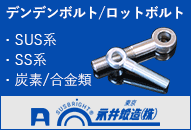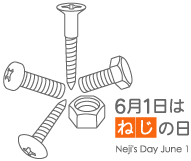2025年も明けて1カ月。各団体の賀詞交歓会や互礼会では、景気回復や業界の飛躍的成長に期待する声が多く聞かれたが、現実に目を向ければ課題は山積。会場で拾った課題を基に情勢を展望してみる。
何といっても最大の不安定要素はアメリカのトランプ政権だ。発足から2週間が経ったが、矢継ぎ早に大統領令を発令するなど、その展開は目まぐるしい。海外製品への関税引き上げを強調するなか、日本製品への影響も懸念される。円安が継続すれば物価高が続き、中小企業の収益は一段と悪化する。生産性向上による収益圧迫の無限ループの競争にも巻き込まれかねない。
その為替相場への不安も聞かれた。思えば2022年あたりから、ロシアのウクライナ侵攻と重なるように円安が強まった。2024年の年初は1㌦=142円台だったが、円安・円高の乱高下を繰り返し、年末は1㌦=150円前後で落ち着いた。輸入に依存する原材料や資材だけでなく、エネルギー価格が高騰。急速な価格上昇に価格転嫁が追いつかず、企業に与えた影響は計り知れない。ここでも一番立場が弱いのは中小企業。価格転嫁が難しく、物価高が倒産に繋がったケースも見られた。
「金利上昇」が与える影響も心配だ。日銀がマイナス金利政策の解除を決定し、政策金利を引き上げた。これを受け、金融機関も貸出金利を引き上げ、これまでの低金利競争から「金利の世界」に戻った。企業の資金繰りに大きな影響はないだろうが、心理的な負担は増す。生産性の低い企業の場合、金利上昇で体力消耗しかねない。低金利下のビジネスモデルから転換できない企業は、生き残りが難しくなる恐れもある。
そして、ここ数年来の課題であり、「いまさら感」無きにしも非ずの人手不足。コロナ禍が明けて経済活動が戻ったことで、一層顕著になっている。社会的には賃上げに動いているようだが、大手企業と中小企業の格差は歴然だ。身の丈を超えた賃上げは資金繰り悪化に繋がり危険を伴うものの、人材確保や待遇改善で退職を防ぐには、賃上げは避けて通れない。結局のところ、安定収益による賃上げ原資確保ができるかどうかになる。
経営者の高齢化が進み、後継者の育成や事業承継への準備も喫緊の課題。高齢化と資金的・人的リソース不足は、地域を問わず全国各地に広がり、深刻さは一層増している。後継者側の能力や経験で差はあるものの、一般的に事業承継には3年から5年は必要といわれる。これが間に合わない場合、事業継続の断念といった選択肢も現実味を帯びてくる。企業が自立し、地に足をつけて将来ビジョンを描くことができるか。それが問われる1年だ。