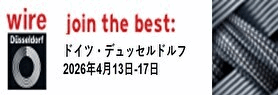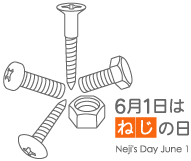米中間の〝チキンレース〟と評される貿易摩擦問題が一段と深刻化する局面を迎えた。今年4月に続き、中国の知的財産権侵害に対抗する貿易制裁の第2弾として、米通商代表部(USTR)が7月23日発動するとした25%の関税上乗せ措置である。160億㌦(1兆8000億円)分の中国の成長産業が標的で、電子部品や産業機械、鉄道車両など計279品目に及ぶ。
中国も直ちに同様の規模で報復関税を課すと公表しているが、トランプ米大統領は中国の出方次第で食料品など別途更に高い関税を課す意向も明らかにしている。特に今回の対中制裁関税の影響は、スマホなど電子部品類はもとより自動車向け電装品にも波及するとみられ、間接的に日本企業にも懸念が広がっている。
自動車の主要部品がメカニカルパーツで占められていたのは1960年代まで。〝マスキー法〟に端を発する排出ガス規制や、オイルショックを契機とした燃費向上ニーズの高まりから、70年代以降エンジンの電子制御技術が飛躍的な進歩を遂げ、次第に電装品のウエイトも大きくなっていった。今では自動車の様々な個所に取り付けられたセンサーが運転者の不注意を知らせてくれたり、カーナビは行く先々の渋滞や回避ルートまで検索、案内してくれる。自動運転化技術が既に実証実験段階にある中、自動車におけるカーエレクトロニクスのコスト比率は今や70%超に及ぶとの指摘もある。それだけに今回のトランプ政権による保護主義的通商政策、貿易摩擦が日本経済の景気の先行きに影を落とす存在としてクローズアップされる。
また直近では、米国と対立するトルコの通貨リラが急落した〝トルコショック〟による影響も不安材料である。日本にとっては欧州市場や同じイスラム圏への活動拠点だけに、国内における円高・株安の招来とともに懸念材料は増すばかり。
他方、これらの影響を受けざるを得ない自動車関連部品業界は、昨年来鉄鋼材料を始めとする素材価格の高止まり感が続いており、メーカー・商社問わず各サプライヤーとも製品価格への転嫁に窮しているのが実情である。また西日本豪雨災害に伴う一部自動車メーカー関連サプライチェーンの寸断は8月中旬現在、未だ全面復旧には至っていない。
かつて日本車バッシング渦にあった米国市場でも現地生産化比率を上げることなどして乗り切ってきた日本の自動車産業だが、今回は世界的にも経済環境的にも〝四面楚歌〟だ。
内閣府が先に発表した2018年4―6月期の実質国内総生産(GDP)一次速報値こそ年率1・9%増と2四半期ぶりにプラス成長を記録したが、日本政府の経済・外交問題に対する〝立ち位置〟とともに、今後の成り行きが注目される。